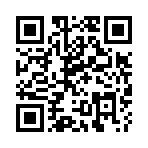2018年04月16日
ヒルズの窓から 第2回 【デフレ?モノの値段】

安くて良いものは増えたけれど、本当に欲しい、必要なものを探すのは、相変わらず大変だ。再任された日銀総裁の新しい任期がスタート、との報に触れ、少し前までよく耳にしたデフレという経済用語と共に、”正しい価格設定”の方法を考えてみた。
デフレとは、モノに対して貨幣の価値が上がった状態のこと。国会質疑で、日本がデフレ状況下であることを示す例として、百均が持ち出されたことがあったのだけど、企業活動として行われている価格設定とデフレとは、直接的に結びつかない様な気がして、当時から違和感を覚えていた。
デフレからは少し脱線するが、企業努力で低価格を実現した発泡酒と第3のビール。酒税見直し案による値上げを巡っては「不味くするのに商品開発するのはアホらしい」との発言も飛び出し、物議を醸した。ナショナルカンパニーともなると、食文化の先導役を担う部分もあろうから、上等な製品を世に送り出す事も確かに重要ではある。一方で発泡酒と第3のビールはヒットしたわけで、結果だけを見れば企業の商品開発は消費者ニーズに応えるものだった。
百均も第3のビールも、商売の基本である薄利多売を実践し、企業として成果を上げた。その事が、景気を悪くする方向に繋がってしまうのだとしたら、何とも不条理だと思うが果たしてそうなのだろうか?

子どもの頃に比べれば、自由になるお金は増えた筈なのに、欲しいモノが何でも手に入るようになったのか、と言えば、私の場合そうでもない。ウインドウショッピングをしていて、目に入るもの、手に取るものにはそれなりの値段がついている事の方が多い。ハンズやロフト、無印良品といった雑貨屋、ドン・キホーテでさえ、だ。むしろ子どもの頃より選択肢が増えて、ため息をつく回数が多くなった気すらする。
それでも、買う時には買う。どうしても欲しい時、必要な時はもちろんだが、値段と価値が釣り合っていて廉価である、つまり販売元が消費者にサービスしてくれていると感じた時だ。
経済活動というのは、売る側と買う側との間でお金を媒体に交わされるコミュニケーションだと思う。円滑で、両者ともにハッピーな受け応えが行われるよう、その入り口となる価格設定を正しく行うためには、誠意を持って消費マインドに訴えかけていくしかない。
提供側でもある私としては、今のところそんな結論に至っている。
Posted by 相沢あやの at 18:11│Comments(0)
│連載
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。